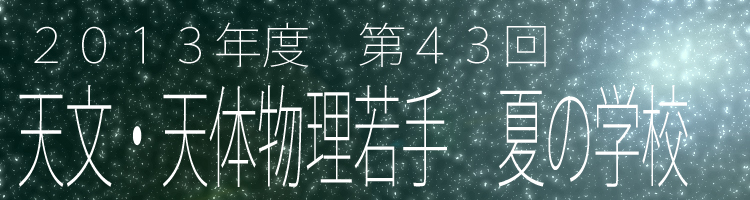
招待講演者一覧と講演タイトル・アブストラクト
招待講演者は各分科会ごとに講演順に掲載しております。
| 重力波で探る初期宇宙 | |
|
分科会:重力・宇宙論 日時:7月30日 16:00-17:00 講演資料 |
講師:黒柳 幸子(東京理科大学) |
| 日本のKAGRAを初めとする世界各地の次世代のレーザー干渉計重力波検出器が数年後の稼働を予定している今、これまで長年に渡って待ち望まれてきた重力波の初検出がいよいよ現実味を帯びてきている。重力波実験において、まず検出が期待されるのは天体現象を起源とする重力波であるが、重力波は宇宙論の検証においても非常に有用でユニークな観測手段となる。その強みは何と言っても透過性の強さにあり、電磁波と違って宇宙の晴れ上がり以前も物質との相互作用が弱い重力波は、CMB以前の極初期宇宙の情報を直接我々に届けてくれる。将来的にeLISAやDECIGOといった宇宙衛星を用いた超高感度の重力波干渉計が実現すれば、重力波実験の宇宙論への応用の幅は大きく広がる。本講演では、新たな宇宙観測の窓として重力波検出実験が初期宇宙に関してどのような情報を提供してくれるのかを紹介し、さらにCMBを初めとする宇宙論的観測と組み合わせることで新しく探れる物理について展望を述べる。 | |
| 銀河形成と宇宙再電離が織りなす初期の宇宙進化 | |
|
分科会:重力・宇宙論 日時:7月31日 11:30-12:30 講演資料 |
講師:大内 正己(東京大学) |
|
赤方偏移z = 1100の晴れ上がり後、主に中性水素ガスに満たされた宇宙は暗黒時代を迎えた。一方で、 QSOに現れる吸収線を用いて現在の宇宙を調べると銀河間の水素ガスはほぼ電離していることが分かっている。つまり、z = 1100で一旦中性になった水素が宇宙史のどこかの時点で電離されたことになる。これが宇宙再電離である。宇宙再電離の原因は未だ明らかになっていないが、第一世代星・銀河とそれに続く銀河形成がもたらす大量の紫外線が再電離を引き起こしたと考えられている。一方で、再電離された空間においては強い紫外線背景光があるため、ハロー内のガスが加熱され矮小銀河の形成が阻害される。このように宇宙再電離と銀河形成は強く結びついているため、これらを同時に理解しなくてはならない。QSOのGunn-PetersonテストやCMBの偏光観測から水素の宇宙再電離は赤方偏移6-11程度の比較的初期の宇宙に起こったことが分かっている。 しかし、宇宙再電離に関する本質的理解は殆ど進んでいない。例えば、 宇宙再電離が比較的短時間で終了するsharp reionizationだったのかその逆のextended reionizationだったのかといった問題、さらには 宇宙再電離の根本的な問題である電離プロセス(大規模構造の中での電離の伝播) に至っては、未だ解決の糸口は見つかっていない。 本講演では、銀河形成を含めて複眼的に宇宙再電離の問題を議論する。その上で未解決の課題を提示し、次世代の21cm輝線やCMB偏光、可視光-近赤外線観測で明らかにされる事柄を概観する。特に、日本の研究者が主導し来春から大規模観測が予定されている可視光超広視野カメラすばるHyper Suprime-Cam探査と関連する大規模数値シミュレーションについて詳しく話し、今後進展が期待される初期の宇宙進化の研究について紹介する。 |
|
| 解き明かされた銀河系宇宙線の起源 | |
|
分科会:宇宙素粒子 日時:7月29日 15:30-16:30 講演資料 |
講師:田島 宏康(名古屋大学) |
|
宇宙線は宇宙から降り注ぐ高エネルギーの素粒子で、109から1020電子ボルト以上まで幅広いエネルギー分布を持ち、その最高エネルギーは、人類が加速器で実現できるエネルギーをはるかに凌駕しているため、その加速物理過程は非常に興味深い謎である。宇宙線生成の物理過程を理解するためには、宇宙線の起源となる天体を同定することが重要であるが、荷電粒子である宇宙線は、乱流状態の星間磁場に影響を受け直進できないため、その到来方向を測定しても起源にたどり着くことはできない。一方で、宇宙線と星間ガスの相互作用で放出されるガンマ線は、星間磁場に影響を受けず直進できるため、宇宙線の起源とその伝播を研究する上で最も有力な手段と考えられている。 2008年に打ち上げられたフェルミ・ガンマ線衛星は、これまでに1800以上のガンマ線源を検出し、ガンマ線宇宙物理学に大きな進展をもたらした。宇宙線起源の研究においても、フェルミ衛星の観測によって決定的な証拠を掴むことができた。超新星残骸は、銀河系内宇宙線起源の最も有力な候補と考えられていることから、フェルミ衛星でW44、W51CやIC443と呼ばれる比較的古い(爆発から数万年以上の)超新星残骸からのガンマ線を観測した。これらの超新星残骸では、その衝撃波が周辺の星間ガスと相互作用をしている兆候が見られたため、宇宙線陽子起源のガンマ線を観測することが期待されていたが、我々が開発した画像解析手法によりW44ではガンマ線が超新星残骸の衝撃波領域から放射されていることを確認した。さらに、W44とIC443において2×108電子ボルト以下の領域のエネルギースペクトルを精密に測定したところ、宇宙線陽子起源のガンマ線に特徴的なスペクトルを捉えることに成功し、超新星残骸で宇宙線陽子が加速されていることを明らかにした。 |
|
| CALETによる高エネルギー電子・ガンマ線観測 | |
|
分科会:宇宙素粒子 日時:8月1日 10:00-11:00 講演資料 |
講師:田村 忠久(神奈川大学) |
| 今年4月にAMSの成果が公表されたのは記憶に新しいところであろう。宇宙線と物質の衝突による二次成分として予想される陽電子の全電子(電子と陽電子の合計)に対する比が、10 GeV以上では予想からはずれて増大することがPAMELA衛星によって発見され、その増大が100 GeVまでは続くことが確認されていた。AMSの結果ではそれがさらに250 GeVまで続いていた。このような陽電子の増大が、暗黒物質の対消滅や崩壊によるものであれば、その質量に応じて、エネルギースペクトルに頭打ちが現れるはずであるが、まだその尻尾をつかんでいない。PAMELAと同時期に、原子核の観測を主目的とした南極周回気球ATICによって600-800 GeV近傍での電子の過剰が報告され、暗黒物質の影響である可能性も示唆されている。これが暗黒物質の質量(崩壊ならこの2倍)なのか?このシナリオはたいへん魅力的だが、ガンマ線衛星Fermiや地上チェレンコフ望遠鏡HESSの結果は、ATICほどの顕著な過剰を示していない。また、パルサー天体が陽電子の過剰の原因である可能性もある。これを解明するには、TeV領域までの高精度なエネルギースペクトルを得る必要があり、日本では、宇宙線としては日本初の宇宙観測となるCALETを宇宙ステーションに搭載する準備が進んでいる。CALETは、超新星残骸での電子加速の直接検証を主目的としており、AMSやPAMELAのようなマグネットは搭載しないので陽電子を選別できないが、電子検出に最適化された観測装置によって高精度のスペクトルを10 TeVまで得ることができる。そのため、暗黒物質やパルサーによる電子過剰の検出も可能である。この講演では、CALETの観測目的や開発状況を他の実験との関連も含めて解説する。 | |
| ガンマ線バーストで探る初期宇宙 | |
|
分科会:コンパクトオブジェクト 日時:7月30日 11:30-12:30 講演資料 |
講師:米徳 大輔(金沢大学) |
|
ガンマ線バースト(GRB)は宇宙最大の爆発現象として知られている。短時間ではあるが極めて明るく輝くため、初期宇宙を探るプローブとして利用されてきている。これまでに分光観測で確認された最高赤方偏移はz = 8.2で、測光観測ではz = 9.4のイベントが確認されている。今後もより遠方の宇宙を観測できると期待されており、z > 10という宇宙で最初の星が誕生した頃の物理情報を得られるだろう。 本講演では、GRBを用いた初期宇宙観測について、2つの着眼点で紹介する。ひとつ目はGRBの後に続く残光現象を利用した分光学的なアプローチで、これはいわば王道の攻め方と言える。赤方偏移z > 7では、水素のライマンα吸収の効果を強く受け、可視光では観測することができない。近赤外線での分光観測が重要となる。残念ながらz = 8.2のGRBでは、赤方偏移の同定には成功したものの、良質な分光スペクトルが得られなかったため、初期宇宙の物理情報は得られていない。ここではz = 6.3で発生したGRB 050904の例を用いて、GRBを用いた観測的宇宙論の展開方法を説明する。 もうひとつは、GRBの突発的ガンマ線放射の特性(Epeak–光度関係など)を利用したアプローチである。我々の研究グループは、これまでにz > 10の星形成率の測定や、宇宙再電離・重元素合成量の議論などを行ってきた。最近では、z > 2の宇宙における宇宙論パラメータの測定を行い、暗黒エネルギー量は時間に強くは依存しない宇宙項のような性質を持っていることを示してきた。このような手法は新しい試みであり、上記の関係式の物理的な起源や、全てのGRBについて成立する普遍的な性質であるのかをきちんと議論しなくてはならないが、将来、暗黒エネルギーの起源(まずは時間発展)を議論する一つの有効な手法と考えている。 |
|
|
爆発的コンパクト天体現象の理論研究: 何がわかっていて何がわかっていないのか? |
|
|
分科会:コンパクトオブジェクト 日時:7月31日 10:30-11:30 講演資料 |
講師:諏訪 雄大(京都大学) |
|
コンパクト天体が引き起こす高エネルギー現象は、極限物理の実験場であると考えられます。そこでは地上実験では到達できない領域の物理が実現されており、これらの現象についての理解を深めることが、高エネルギー・高密度物理の世界に迫るための手段になることが期待されています。特に、超新星爆発やガンマ線バーストといった激しい爆発現象の中心部は、我々の知っている全ての相互作用(重力・電磁気力・弱い力・強い力)が同時に重要な働きを及ぼす、極めて複雑かつ面白い状態になっています。それゆえ、いまだ爆発がどのように引き起こされているのか、完全にはわかっていません。 本講演では、超新星爆発とガンマ線バーストの中心エンジンについて、いまどこまで解明されているのか、またどんな謎が残っているのか、についてお話ししたいと思います。 |
|
|
ブラックホール周囲の降着・噴出流はどこまでわかったか? 〜最新の成果と課題〜 |
|
|
分科会:コンパクトオブジェクト 日時:8月1日 9:00-10:00 講演資料 |
講師:大須賀 健(国立天文台) |
|
ブラックホールの周囲では、吸い込まれるガスの重力エネルギーが解放され、強力な放射や高速なガスの噴出現象が引き起こされている。極めて小さな領域で膨大なエネルギーが解放されるため、活動銀河核やX線連星、ガンマ線バーストといった高エネルギー天体現象のエンジンであると考えられている。また、この膨大なエネルギー放出は銀河の進化に影響を与えるであろうことから、近年話題となっている巨大ブラックホールと銀河の共進化の起源ではないかと期待されている。 ブラックホールの重力に引きつけられたガスが円盤を形成しつつ吸い込まれ、膨大なエネルギーを解放するといういわゆる降着円盤の理論は1970年代に構築された。幾つもの観測事実を説明することに成功したことで世界中で信じられるようになったが、あくまで現象論的なモデルであり物理的に解明したとは言い難い状況であった。しかも、近年になって説明できない観測事実も次々に報告されるようになった。 現象論的な研究に甘んじてきたそれまでの状況を打開する鍵は磁場と放射の扱いである。 従来の研究では放射や磁場、多次元効果は無視もしくは極めて簡易的に扱われてきた。しかし、それでは問題の本質に迫ることはできない。そもそもガス降着には角運動量輸送が必須であるが、それは磁場によって引き起こされる。磁場は円盤内の乱流を助長するだけでなく円盤表面からのガス噴出現象を引き起こす場合もある。円盤の放射効率が円盤の形状や明るさを決めるし、放射圧でジェットが噴出する場合もある。重力や流体に加えて放射や磁場を空間多次元で正しく扱うこと、即ち多次元放射磁気流体力学計算が必要不可欠なのである。ただし、放射磁気流体力学計算は物理が難解で計算量が膨大なため、実現可能となったのはごく最近である。 本講演では、多次元放射磁気流体力学シミュレーションによって見えてきたブラックホール降着・噴出流の最新の描像を紹介する。そして残された課題と今後の発展についても議論する。 |
|
| 円盤銀河の何が問題か?–天の川銀河から遠方銀河まで– | |
|
分科会:銀河・銀河団 日時:7月30日 13:30-14:00 講演資料 |
講師:井上 茂樹(韓国天文宇宙科学研究院) |
|
「我々が住んでいる天の川銀河は最も観測しやすい銀河であり、そのため円盤銀河は最も理解の進んでいる銀河の種類である」という文言がよく耳目に触れる。私自身も研究提案書などを書く際には似たような文章をついつい書いてしまう。だが、はたして本当にそう言えるだろうか?例えば、実は銀河中心距離や銀河回転速度の測定は、宇宙年齢や暗黒エネルギー密度などの宇宙論パラメータの測定よりも精度が悪かったりする。天の川銀河のバルジの質量も観測ごとでバラバラだったりもするし、thick discや球状星団といった、古くから存在がわかっていながら形成プロセスが未だに不明な構造もある。そもそも力学的に低温な構造である銀河円盤は、銀河同士の激しい衝突・合体を基調とする階層的構造形成論とは一見すると相反するものであるとも言えるし、一体どのようにして形成されたのであろうか? 夏の学校は若い学生さんが多く集まる場であり、まだ研究テーマも決まってないような参加者も多いと思います。そんな場ではより多くの人に話題を提供できるような広く浅い内容の方が良いかもしれないと考えました。本講演では円盤銀河研究の現状や今後の展望に関して、天の川銀河から遠方宇宙の銀河形成段階にいたるまで、円盤銀河に関するできるだけ広い範囲をレビューする予定です。出来るだけ新しい話題を紹介し、若い人たち(私もまだ若いはずですが)が今後解決して行くべき円盤銀河形成論の問題点を紹介する予定です。 |
|
| 渦巻銀河ダイナミクス理論の進展と天の川銀河 | |
|
分科会:銀河・銀河団 日時:7月30日 14:00-14:30 講演資料 |
講師:馬場 淳一(東京工業大学) |
|
渦巻銀河の渦状腕を形成し維持する物理機構は,銀河物理学の最大の謎の一つである.その最も有力な説に「密度波仮説」がある (Lin & Shu 1964, 1966).これは恒星系円盤を連続体と見なし,渦状腕を恒星系円盤の表面を伝わる定常的な「疎密波」とする仮説である.Lin & Shuによるきつく巻き付いた渦状腕の局所線形近似による密度波の分散関係の導出を契機に,その後,大局モード解析,減衰や励起機構の解析など,恒星系渦状腕に関する様々な理論研究が行われてきた.しかし,密度波の物理過程については未解決の問題も多く,十分に解明されたとは言いがたい. 一方で,今後,天の川銀河の恒星系の大規模撮像・分光サーベイやアストロメトリが進み,個々の星の位相空間データから,渦状腕構造に関して科学的研究が行われることになるだろう.したがって,古典的な線形・定常・連続体という扱いから脱却し,非線形・非定常・多体系の視点から,渦巻構造の持続性と維持・増幅機構,渦状腕と星間ガスの相互作用などの解明を試みることが,渦状腕構造の真の解明,そして渦巻銀河ダイナミクスの新展開へと導くと考えられる. このような研究背景のもと,私は特に渦巻銀河・棒渦巻銀河のダイナミクスに着目し,恒星系円盤の重力多体系ダイナミクスと,星間ガスの自己重力,放射冷却や加熱過程,星形成や超新星爆発といった重要なプロセスを組み込んだ銀河円盤全体の高精度3次元数値シミュレーションを行い,天の川銀河の棒状構造や渦状腕構造やmulti-arm 型渦巻銀河のダイナミクスなどに関する研究成果を挙げてきた.本講演ではこれまでの渦状腕研究をレビューしながら,最新の天の川銀河の大規模シミュレーションの紹介や今後の計画を述べる予定である. |
|
| 塵に埋もれた宇宙の星形成 | |
|
分科会:銀河・銀河団 日時:7月31日 14:30-15:00 講演資料 |
講師:廿日出 文洋(国立天文台) |
|
遠方宇宙における星形成活動の研究は、これまで主に可視光や近赤外線を使って進められてきました。しかし、可視光や近赤外線はダストによって大きく吸収を受けるため、宇宙における星形成活動の多くが見逃されている可能性があります。そこで重要なのがミリ波・サブミリ波です。ダストに吸収された星の光は、赤外線~ミリ波・サブミリ波の波長帯で再放射されます。このダストからの放射を観測することによって「埋もれた」星形成活動を暴き出すことができます。 私たちのグループは、南米チリにあるアステ望遠鏡(Atacama Submillimeter Telescope Experiment; ASTE)を用いてサーベイ観測を行い、1000個を超えるミリ波・サブミリ波で明るい銀河「サブミリ波銀河」を検出しました。サブミリ波銀河はダストに厚く覆われた巨大な銀河で、星形成率は数100–1000 Msun yr–1という非常に活発な活動を行っています。その激しい星形成や赤方偏移分布(z〜2–3)などの特徴から、現在の宇宙に存在する大質量楕円銀河の祖先ではないかと考えられており、銀河進化を研究する上で重要な種族です。 一方で、サブミリ波銀河は特殊な銀河であり、宇宙に存在する銀河の全体像を捉えるには、ミリ波・サブミリ波で暗い、より「一般的な」銀河を観測する必要があります。そこで期待が寄せられているのがアルマ望遠鏡(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array; ALMA)です。現在建設と並行して初期科学運用が行われていますが、既に世界最高性能のミリ波・サブミリ波望遠鏡です。私たちのグループは、アルマ望遠鏡を使って従来よりも約10倍暗い銀河を検出し、個数密度を測定しました。検出された銀河はサブミリ波銀河と比較して穏やかな星形成活動をしていると考えられます。従来見つかっていた爆発的星形成銀河と、一般的な星形成をつなぐ銀河が検出されたことは、銀河の形成過程や宇宙の星形成活動を明らかにする上で大きな前進です。 本講演では、ダストに埋もれた星形成活動のこれまでの研究、および今後の展望についてお話しします。 |
|
| 「すざく」衛星による銀河団外縁部の観測 | |
|
分科会:銀河・銀河団 日時:7月31日 15:00-16:00 講演資料 |
講師:松下 恭子(東京理科大学) |
|
銀河団は、重力的に束縛されたものとしては宇宙で最大の構造であり、冷たい暗黒物質の重力により形成される。銀河団の力学的進化の時間スケールは宇宙年齢と同程度である。よって、銀河団は現在も、宇宙の大規模構造のフィラメントに沿った銀河団同士の合体や小さな系の降着により成長を続けていると考えられている。銀河団では、バリオンのほとんどは、数千万度の高温プラズマとして、銀河団を満たしている。そのため、銀河団はバリオンが主要な役割をはたす熱的、化学的進化の実験室ともいえる。バリオンが冷えて星が形成され、銀河が形成される。超新星爆発や活動銀河核の放出するエネルギーが銀河の外のバリオンにフィードバックされ、銀河団ガスの温度やエントロピーを増加させる。さらに、超新星爆発によって合成された重元素が銀河間空間に供給される。したがって、銀河団ガスの温度やエントロピー、重元素の分布を調べることにより、銀河団の熱的な歴史や星形成史を探ることができる。 銀河団の力学的半径であるヴィリアル半径は、大規模構造と銀河団の境界ともいえる。よって、ヴィリアル半径に近い領域では、最近の銀河団進化の情報を保持しているはずである。そもそも、銀河団のほとんどの暗黒物資と銀河団ガスは銀河団の外縁部に存在している。2005年に打ち上げられた日本のX線天文衛星すざくは低く安定するバックグラウンドを誇る。すざく衛星を用いて、銀河団のヴィリアル半径までの銀河団全体の高温ガスの物理量を求めることが可能となった。このすざく衛星の成果を紹介する。 |
|
| 星震学の進展 | |
|
分科会:太陽・恒星 日時:7月29日 17:00-17:30 講演資料 |
講師:柴橋 博資(東京大学) |
|
星の研究は天文学の基本である。が、望遠鏡で星の観測をしても、星の内部を見ることは出来ない。20世紀前半を代表する天文学者のエディントンは、「一体、どんな装置で星の中を調べられるというのか?」と反語的に書いている。彼の用意した答えは、「理論」だった訳だが、それから4分の3世紀を経た今日の私達は、「星の振動を使って、目では見えない筈の星の内部を見る」、という答えを探し出した。 星の振動というのは、古くから、明るさが周期的に変化する変光星として知られていた。この変光の仕組みは、エンジンや熱機関と似ている。今、星を収縮させたとする。普通の場合には、温度が上がって、星から放出する輻射が増えてしまい、それによるエネルギー損失のために収縮が膨張に転じても元に戻りきらず、振動が長続きすることはない。ところが、収縮の際に温度が上がっても輻射を外に逃がさずに貯めておき、膨張に転ずるときにそれを吐き出すエンジンの様な仕掛けがあれば、星は自励的に振動をしだす訳だ。こうした仕組みは、特定の大気温度の星でしか起らない。それら特定の星というのが古典的変光星という訳である。 古典的には変光星とは看做されなかった星でも、別の仕組みで振動が起きていることが判って来た。表面に対流層があると、乱流から音波が発生する。音波が星の表面層の至るところで常時発生し、それらが星全体を伝播し巡っているのである。二次元的な像を見ることが出来る太陽の場合には、この音波振動を観測することによって、太陽の内部構造を「見る」ことが出来る様になり、「日震学」として目覚ましい進展を遂げた。 この成功を一般の星に進めるべく、今は「星震学」が大きく羽撃こうとしている。ケプラー衛星による高精度長時間に亘る膨大な数の星の観測データは、量的にも質的にも従前の精度を圧倒的に凌駕する、正に革命的なものである。それに伴い様々な研究が進む星震学の様子を伝えたい。 |
|
| 太陽活動現象が地球に与える多彩な影響 | |
|
分科会:太陽・恒星 日時:7月29日 17:30-18:00 講演資料 |
講師:片岡 龍峰(国立極地研究所) |
| コロナ質量放出やコロナホールは、それぞれ台風や寒冷前線に喩えられるような、太陽風の特徴的な構造をなして地球を数日間包み込み、磁気嵐と呼ばれるオーロラ活動の嵐を引き起こします。磁気嵐が発達する主相ではカラフルなオーロラが地球規模で広がると同時に、静止軌道付近に捕捉されていたヴァンアレン帯の相対論的電子の補足が解かれ一旦消失します。磁気嵐の回復相に入るとオーロラ活動は弱まり、ヴァンアレン帯の電子は複雑なプラズマの波動粒子相互作用によって再生されていきます。コロナ質量放出が、かなり高速の場合に限って、この一連の流れに太陽高エネルギー粒子の嵐が加勢します。これらの、1)オーロラ粒子、2)ヴァンアレン帯粒子、3)太陽高エネルギー粒子は、磁気流体近似では理解できないプラズマ物理学的な面白さが一番の研究対象ですが、実際問題、宇宙機の様々な障害、宇宙飛行士やパイロットの被ばく、オゾン破壊、ひどいときには停電まで、多彩な影響を地球に及ぼしてきた犯人たちでもあるため、宇宙天気予報と呼ばれる実際的な研究も発達してきました。本講演では、このような身近で複雑な宇宙に関する研究の背景をお伝えしたのちに、A)マウンダー極小期のように極端に弱い時にどうなるか、B)キャリントンフレアのように極端に強いときにどうなるか、C)分子雲や超新星に太陽系が突っ込むときにどうなるか、について考察します。あとは時間がゆるす限りオーロラ観測の魅力を語るなり、質問に応じて自由に対話するなりできればと思っています。 | |
| 太陽フレアはいつ起きるか? | |
|
分科会:太陽・恒星 日時:7月30日 9:00-9:30 講演資料 |
講師:草野 完也(名古屋大学) |
|
太陽フレアは太陽表面で発生する太陽系最大の爆発現象であり、電力伝送網などの社会システムにも致命的な影響を与え得る。そのため、その発生予測は科学研究としてのみならず社会的にも重要な課題である。しかし、フレア発生のトリガ機構は未だに解明されていないため、いつ、どこで、どれ程のフレアが発生するかを正確に予測することはできていない。本講演では太陽フレア発生のトリガ機構に関する最近の研究について解説し、精密な観測に基づいてフレア発生を予測する試みについて紹介する。 フレア・トリガ機構の理解を阻んできた最大の困難は太陽磁場の複雑さにある。フレアは太陽活動領域において磁気極性が反転する極性反転線(PIL)を跨いで発生すると共に、複雑な磁場構造を持つ領域で発生しやすい傾向があることが指摘されてきた。しかし、観測された磁場があまりにも複雑なため、どのような複雑さがフレア発生に関係するのかを明らかにすることはできなかった。我々はこの問題を解決するため、約160通りの様々な磁場構造について3次元電磁流体シミュレーションを実施し、フレアのトリガとなる磁場構造を探った。その結果、強い磁気シアと特徴的な磁場擾乱の組み合わせがフレア発生の条件となることを発見した。この条件を満たすと、PILに沿ったヘリカル磁束が自発的に形成され、これが不安定化する結果としてフレアが発生することが分かった。 さらにこの結果を検証するため、我々は「ひので衛星」がこれまでに観測したフレアの発生領域における光球面磁場の詳細構造を解析した。その結果、観測条件の良い大型フレア全てについて、フレア発生領域にシミュレーションより予言された磁場構造が存在することを確認した。上記の結果は詳細な磁場観測によってフレア発生を予測し得ることを示唆している。講演では将来におけるフレア予測の展望と、天文学における予測研究の重要性についても言及する。 |
|
| 恒星進化の理論とその応用 | |
|
分科会:太陽・恒星 日時:7月31日 17:30-18:00 講演資料 |
講師:須田 拓馬(国立天文台) |
|
恒星は宇宙を構成する基本要素の一つであり、可視光で見える天体の大部分を占める。また、恒星からの光のエネルギーは内部での原子核反応によって賄われており、恒星は宇宙の物質を作る現場でもある。従って、恒星の性質を理解することは宇宙の進化を理解するうえで重要である。恒星進化の理論的研究は天文学の中でも歴史が古く、基本的な性質についてはかなり解明が進んでおり、一次元球対称の仮定のもとでは理論はほぼ確立されたと言える。また、恒星の数値シミュレーションでは、一次元球対称に熱対流を考慮した標準モデルが広く使われており、多くの観測を説明するのに成功を収めてきた。恒星の観測は、すばる望遠鏡のような地上大型望遠鏡によって高分解能分光観測が可能となっており、より遠くの星についてより詳細な元素組成分布を知ることが可能となっている。 本講演では、恒星進化理論に基づく数値シミュレーションの現状についてレビューする。さらに、恒星モデルを応用した研究(と関連する観測)についてできるだけ幅広く紹介したい。本講演で取り上げるトピックは以下のものを予定している。(1)宇宙初期に誕生した恒星の観測と恒星進化モデルによる銀河系化学進化への影響、(2)連星進化の種族合成モデルで探る銀河系の星形成史、(3)回転している大質量星の構造と進化、(4)恒星進化理論によるヘリウム三体反応核反応率への制限、(5)銀河系球状星団中の恒星の観測と恒星モデルに基づく星団の起源と形成のシナリオ、(6)低金属量Super AGB星の銀河系化学進化への影響、(7)r-過程元素合成で探る銀河系初期の化学進化。なお、講演時間の制限があるので、この中からいくつかを選んで比較的詳しく紹介し、それ以外はごく簡単な紹介に留める。また、恒星進化理論とシミュレーションについて学ぶための文献と、恒星モデルや観測データを活用するためのツールの紹介も行う。 |
|
| 星間衝撃波の物理と天文学的応用 | |
|
分科会:星間現象 日時:7月29日 18:00-19:00 講演資料 |
講師:井上 剛志(青山学院大学) |
| 天体現象の多くは非常に動的であり、衝撃波と呼ばれる小さなスケールで物理量が突然変動する構造が普遍的に発生する。通常の流体力学とは異なり、星間媒質に代表されるような宇宙プラズマ中では磁場の効果や輻射過程を介した加熱冷却、宇宙線による非熱的効果、自己重力等の様々な物理を考慮しなければならない。これらの効果を考えると、例えば超音速飛行機が発生させるソニックブームの様な空気中では安定に伝搬する衝撃波も場合によっては不安定となり、その不安定性が様々な天体現象にとって本質的に重要になる場面が多々存在する。本講演ではなぜ衝撃波が発生するのかという基本的なところから出発して、宇宙プラズマ中での様々な衝撃波の不安定性やそれによって引き起こされる天体現象のダイナミクス(例えば星間雲の形成、大質量星形成、超新星残骸、ガンマ線バースト等)を著者の最近の研究成果を交えながら解説する。 | |
|
天の川銀河中心領域のX線観測: 巨大ブラックホールの過去の大爆発の証拠を捉えた! |
|
|
分科会:星間現象 日時:7月31日 9:00-10:00 講演資料 |
講師:信川 正順(京都大学) |
|
天の川銀河の中心領域(銀河中心)にはX線を放射する分子雲が存在している。低温(10-100 K)の分子雲が自らX線を放射することはないので、銀河中心の巨大分子雲が高強度の高エネルギー粒子に照らされているという驚くべき事実を示すものであった。 その起源として、巨大ブラックホール射手座A*の過去のX線フレア(Koyama et al. 1996; Murakami et al. 2000)や、低エネルギー宇宙線電子(Yusef-Zadeh et al. 2002; 2007) が提案されていたが、これまでに観測的決定打はなかった。 そこで、我々はX線天文衛星「すざく」を用いた観測を行い、(1)鉄以外の中性元素輝線の発見(Nobukawa et al. 2010)、(2)X線を用いた分子雲の分布の測定(Ryu et al. 2009)、(3)分子雲からのX線放射の時間変動の発見(Inui et al. 2008; Nobukawa et al. 2011)、という成果を挙げてきた。これらの観測事実から、射手座A*が数百年前に現在の100万倍以上の大フレアを起こし、分子雲をX線で照らしていること以外に考えられないことが分かった。本講演では「すざく」によるこれまでの研究の経緯とその詳細な成果を報告する。 本研究成果は主に私が大学院在学時に行ったものである。天文・天体物理学のみならず広い分野から高い評価を受け、第1回日本学術振興会育志賞を受賞している。 |
|
| NANTEN望遠鏡の見た宇宙 | |
|
分科会:星間現象 日時:8月1日 12:30-13:30 講演資料 |
講師:立原 研悟(名古屋大学) |
|
名古屋大学の電波天文学グループでは、チリ・アタカマ砂漠に設置した口径4mのNANTEN2望遠鏡を使い、南の空にあるさまざまな天体に対し、ミリ波・サブミリ波の波長で観測を行っています。特に広視野をいかしたCO輝線の大規模サーベイでは、銀河面や大小マゼラン銀河の分子ガスの姿を明らかにしてきました。最近の成果をご紹介します。 大質量星は周囲の星間物質に対し大きな影響を及ぼしますが、その形成のメカニズムはあまり研究がすすんでいませんでした。大質量星形成領域の分子雲に、あまり初期条件が保存されていないという困難があるためです。外的要因による誘発モデルがいくつか提案されてきましたが、観測的に確立されるには至っていません。私達は分子雲の衝突で大質量星形成が誘発されている証拠を見つけました。銀河系内では少なからぬ頻度で分子雲が衝突し、大質量星形成が誘発されていると考えられます。Spitzer宇宙望遠鏡で同定された多くのシェル状構造を網羅的に観測し、定量的分析を始めています。 星間ガスの運動は、超音速乱流的であると言われています。ガスの音速より大きな線幅をもつ分子スペクトルが至る所で観測されるためです。この乱流が長時間維持されることの理論的説明は、なかなか成功しませんでした。しかし非常に有望な二相乱流モデルが提唱され、分子雲の縁の微小な構造の発見も、このモデルをサポートしています。すなわち高温低密度の原子ガスから、低温高密度の分子ガスができ、両者が共存しているのです。 他にもガンマ線の観測との共同研究から、超新星残骸において高エネルギー陽子が高効果的に加速され、星間物質中の陽子と衝突することで、高エネルギーガンマ線の起源となることを突き止めました。多波長の観測データや理論モデルと組み合わせることで、星間現象の理解は近年飛躍的に進んだと言えるでしょう。 |
|
| 原始惑星系円盤の愉しみ | |
|
分科会:星形成・惑星系 日時:7月29日 14:30-15:30 講演資料 |
講師:武藤 恭之(工学院大学) |
|
原始惑星系円盤は、惑星形成の現場として観測・理論の両面から活発に研究がされている。原始惑星系円盤は、ガスとダスト(固体粒子の成分)から成っており、この中でダストが集積し、最終的にガスが散逸することによって惑星系が出来上がると考えられている。しかし、原始惑星系円盤がそもそもどのような姿をしているのか、またその中でどのような物理過程が起こって多様な惑星が形成されるのか(またはされないのか)という基本的な部分で多くの謎が残っている。 本講演では、原始惑星系円盤に関する基礎的な理論や最新の観測結果について、特に「原始惑星系円盤の物理構造と進化」をキーワードとしながら概説する。具体的には:
といった話題を、講演者自身の研究も交えながら簡単に紹介したい。 |
|
| まだ見ぬ世界と生きているうちが華の系外惑星探査 | |
|
分科会:星形成・惑星系 日時:7月30日 16:00-17:00 講演資料 |
講師:河原 創(東京大学) |
| 私が系外惑星に足を突っ込んでから高々数年、その間、第二の地球候補が続々と見つかってしまった。でもその中に、本当に人の心を打つような世界は待っているのだろうか?本講演では、地球型系外惑星探査の方法論や現状をお話ししたい。特に惑星の表層環境をいかに知るか、生命由来と考えられるシグナルは何か、等の課題は、私たちが生命であるがゆえに、何か特別な興味を引き起こす気がする。このような探査法の中には、ちまたで聞かれる予算予算予算や縮小中止廃止のニュースと比して、到底現実味のなさそうに思えるものも含まれているかもしれない。しかし、思い出してほしい。人類は40年以上前に月に降り立ったらしいし、私がたかが72歳になる予定の40年先には何が起こるか分からないではないか。それから、検出可能性をうじうじする机上の理論だけではなく、具体的に10年オーダーの未来にできうる一歩として、晩期型星周りの地球型惑星の直接観測計画、SEIT計画を主に楽観的な若手で進めている。始まったばかりの挑戦的な装置開発や楽観的すぎる探査計画をより現実に近づけることなどに興味を持ってもらえるようにがんばります。 | |
| 銀河系と初期宇宙での星形成 | |
|
分科会:星形成・惑星系 日時:8月1日 11:00-12:00 講演資料 |
講師:細川 隆史(東京大学) |
| 星は様々な天体の中でも最も基本的なものであり、その形成過程についての研究は長い歴史がある。この講演では、これまでのこの分野の研究の進展を踏まえつつ、これからの研究がどのように進んで行くか、どのような研究が大きな成果につながるか、など主として理論研究を中心に将来展望にも重点をおいて紹介する。銀河系の星形成について標準シナリオの受け入れられている低質量星(〜 1 Msun)の形成、謎の多い大質量星(OB型星)の形成過程について触れたのち、後半では初期宇宙での星形成過程について銀河系での星形成過程との類似点、相違点を明らかにしつつ説明する。宇宙の再電離、巨大ブラックホールの起源、初期宇宙から現在の宇宙に至る 宇宙論的時間での星形成過程の進化など、関連する話題にも時間の許す限り触れる。 | |
| 補償光学系の可能性 | |
|
分科会:観測機器 日時:7月30日 14:30-15:30 講演資料 |
講師:秋山 正幸(東北大学) |
| 現在の8-10m級の地上大型望遠鏡では補償光学系が観測に定常的に使用されている。2020年代の Thirty Meter Telescope をはじめとする 30m 級の次世代超大型望遠鏡の時代には、その大口径の空間分解能や集光力を最大限に生かす上で、補償光学系は必須の技術となる。補償光学系による観測は天空にある星を用いて補償を行う自然ガイド星補償光学系から始まり、観測対象を広げるためにレーザーガイド星補償光学系へと発展し、またさらに多層共役補償光学系、極限補償光学系、多天体補償光学系、地表層補償光学系などいろいろな形で特化した補償光学系の検討や実現へと広がってきた。この講演ではまず大気揺らぎの性質と補償光学系を用いた観測の基本的な性能や制約について紹介する。その後で、世界の様々な天文台で現在進行している次世代の補償光学系の開発について紹介する。最後に我々のグループで行っている TMT の多天体補償光学系やすばる望遠鏡の地表層補償光学系の開発や検討の状況を紹介したい。この講演からぜひすばる/Keck/Geminiに補償光学系を用いた観測のプロポーザルを出すことや補償光学系を開発することに興味を持ってもらえればと思います。 | |
| 宇宙マイクロ波背景放射偏光望遠鏡の先進テクノロジー | |
|
分科会:観測機器 日時:7月31日 16:00-17:00 講演資料 |
講師:都丸 隆行(高エネルギー加速器研究機) |
|
宇宙マイクロ波背景放射(CMB)は初期宇宙を探る有力なツールであり、WMAPやPLANK衛星による観測結果から高精度な宇宙論パラメータ決定がなされている。現在CMB観測でもっとも注目されているのは、B-modeと呼ばれる鏡非対称な偏光パターン探査であり、特に空間スケールの大きなB-modeパターンは原始重力波により生成され、インフレーションモデルを決定できる可能性が指摘されている。このため、世界中で熾烈な競争が行われている。 我々のグループでは2012年からチリ・アタカマ高地でCMB偏光望遠鏡POLARBEAR(PB-1)を運用しており、またそのアップグレードレシーバーであるPOLARBEAR-2(PB-2)を開発中である。POLARBEAR実験では、極めて高感度な超伝導Transition Edge Sensor(TES)ボロメータアレイを導入している。超伝導の転移端を用いた高感度光センサーは1940年代には提案されていたが、あまりに転移幅が狭いため実用化していなかった。しかし、1990年代に伝熱フィードバック法が開発されて実用化がすすみ、PB-1では世界最多の1274コのTESボロメータを搭載するに至っている。(PB-2では7588コのTES搭載を目指している。)PBのTESボロメータは転移温度が約500mKであり、ソープション冷凍機を用いて冷却されている。ソープション冷凍機は冷凍能力が小さいため、光学ウィンドウからの熱侵入を押さえるための赤外線カットフィルターや断熱シールドなどにも先進技術が用いられている。また、低インピーダンスのTESを機能的に読み出すために、SQUIDアンプおよび周波数ドメインマルチプレキシングといったreadout技術も研究されている。本講演では、CMB偏光観測について概要を述べると共に、その中で用いられている先進技術について講演する予定である。 |
|





